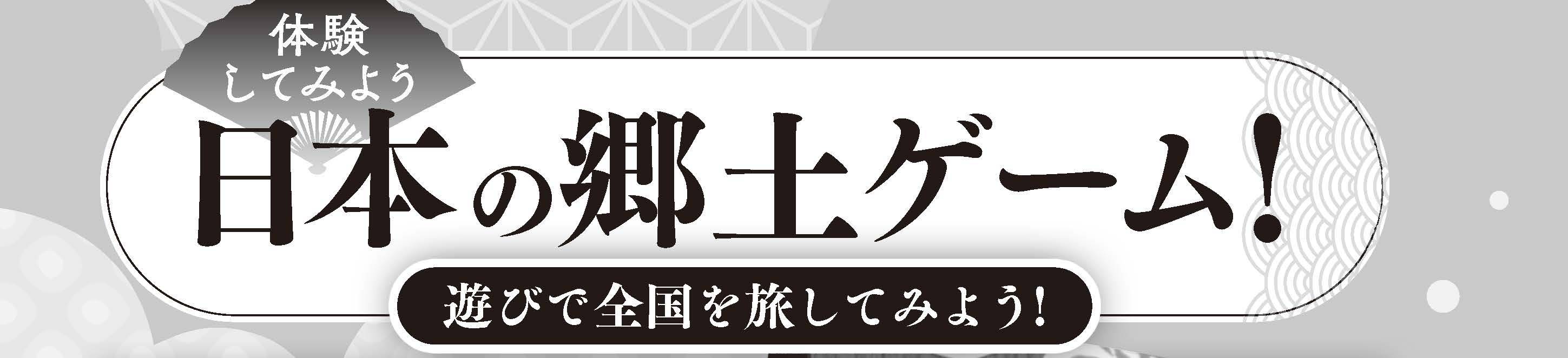伝統ゲーム(郷土ゲーム) kyodogame
ブース概要
◇全国11の郷土ゲームが集まり、ゲームの紹介、展示、販売、試遊などを実施します。
参加する11の郷土ゲーム:
下の句かるた(北海道)、ゴニンカン(青森)、投扇興(東京)、八八(神奈川)、ごいた(石川)、旗源平(石川)、モザイク(岐阜)、カロム(滋賀)、盤双六(京都)、かりうち(奈良)、島札(沖縄)
◇今回も郷土ゲームスタンプラリーを開催!
詳細は追って告知いたします。
出展コメント
◆下の句かるた(北海道全域)“北海道民の熱いスピリット”
北海道で百年以上遊ばれている百人一首。何と下の句を読んで下の句を取るのだが決して簡単ではない。取り札は板で、変体仮名で書かれている。慣れてないと取るどころか読むことも難しい。これを道民は3対3のチーム戦で豪快に取る。
◆ゴニンカン(青森県五所川原市ほか)“青森県民の深~い関係”
青森で昔から遊ばれている5人のトリックテイキングゲーム。AKQJの16枚の絵札を2人の「カンケイ」と3人の「ムカンケイ」が熾烈に取り合う。素早く仕掛ける「スコンク」とそれに続く「十六」が醍醐味。
◆投扇興(東京都台東区浅草ほか)“扇が一閃、雅な見立て”
江戸時代中期に、投壺という古代の遊びから京都の粋人が考案したと伝えられる歴史のある遊び。
的に正確に当てるのが目的と思われやすいがそうではなく、落ちた的と扇の姿を源氏物語五十四帖になぞらえて見立てて採点する雅びたゲーム。
◆八八(神奈川県横浜市)“花札遊びの最高峰”
百種を超える花札ゲームの中で、最も面白いと言われるのがこの八八。一名らしゃめん花とも呼ばれ、明治20年頃に横浜の遊郭で完成したと伝えられている。面白いだけにルールは複雑で、今回はその花札の粋を体験できる数少ない機会。
◆ごいた(石川県鳳珠郡能登町宇出津)“その魅力に取り憑かれると駒が離せない”
明治初期から石川県能登町宇出津にのみ伝わってきた伝承遊戯の粋「ごいた」。日本のゲームには珍しい、ペアで互いの意志が通じ合った時の面白さは他のゲームに代えがたい。いつまでもプレーしていたくなる危ない遊び。
◆旗源平(石川県金沢市)“独特の囃し言葉で盛り上がる伝統ゲーム”
加賀藩の時代より武士から庶民まで正月遊びとして伝承された、文字通り郷土のゲーム。源氏と平家に分かれ、賽を振り合って大旗・小旗、そして纏を取り合う。加賀ならではの囃し言葉で大いに盛り上がること間違いなし。何と言っても前田様の御紋、梅が一番!
◆モザイク(岐阜県多治見市)“ゲームシステムと伝統技術の出会い”
昔から有名な伝統の焼き物技術と、巧みなゲームシステムがここ多治見で出会った。伝統の技術は新たな用途に向かって広がり、面白くて深いゲームシステムは美麗なコンポーネントを得て深みを増す。新たに生れ出た郷土のゲーム。
◆カロム(滋賀県彦根市)“彦根の巧みな技の結晶”
おそらく明治期に海外から伝わり、なぜか彦根で熟成して定着し、長く愛され遊ばれ続けた高度なおはじき。狙いや弾き方の正確さのみならず、互いの駒の位置関係から巧みな作戦を生み出す、技術と頭脳のゲーム。
◆盤双六(京都府ほか)“千年の歴史の重み”
飛鳥時代に日本に伝わり、千年の間、人々を熱中させた和風バックギャモン「盤双六」。二個の賽を交互に振って十五個の自分の駒を進め、全て自陣に戻す。このとき互いの駒の道行が交差することで戦略とドラマが生まれる。
◆かりうち(奈良県)“出土した日本古代のゲーム”
二面賽を四つ振って自分の駒四つを上りにもっていく、日本古代の回り双六。時代は思い切り飛ぶが、四枚の金将を振って将棋盤の外周を回る振り将棋のよう。長い長い年月、土の下に埋もれていた「かりうち」で遊ぶと、古代人の心が分かるかも。
◆島札(沖縄県うるま市具志川)“江戸時代の技法を今に残す”
沖縄の具志川にのみ伝わる、江戸時代のルールを今に伝えるメクリ技法。札はとても見やすく、ルールはシンプルかつ花札の基礎中の基礎なので分かりやすい。3人はもちろん4人でも遊べるのは魅力。
その他
https://x.com/home